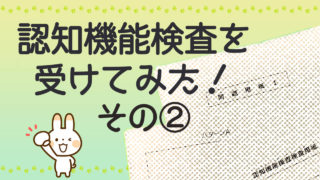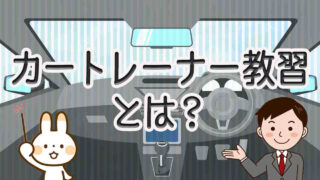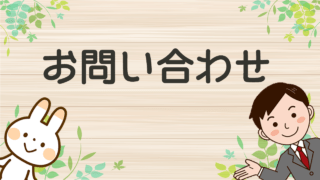この記事は、2022年(令和4年)5月13日に変更になる前に行われていた認知機能検査のアーカイブです。
現在は「時計描画」は行われません。
参考までにご覧くださいね(^^)
>> 【チェック!】新しい高齢者講習(実車試験)の対象になるか調べてみる
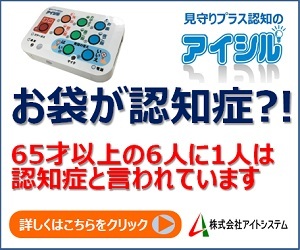
【認知機能検査】もったいない間違え方!イラストを覚えてくると検査のときに混乱する
認知機能検査でよく見かける「もったいない間違え方」をお伝えします。
私たちは認知機能検査のお試しをし、どんな内容の検査をするのかを体験するために、何冊かの本を紹介しています。
これらの本は認知機能検査を自宅で試してみる場合は最適です。.
ただ、丸暗記をしてきたために、本番の認知機能検査で暗記したものをとりあえず書いてしまう、とてももったいない間違え方をよく見るのです。
例にあげて見ていきましょう。
もったいない間違え方を説明しますね!
「戦いの武器」の回答を記入するとします。
あなたが「戦いの武器」を全て暗記してきた場合、記憶の混乱が起こってしまう可能性があるのです。
もちろん、ご本人は全く間違えているとは思ってもいません。
暗記してきて全部回答できた!
きっと大丈夫だわ〜。
これは・・・!
もしかすると回答を覚えてきているかもしれない間違え方だなぁ。
お家などで少し試してみて大丈夫そうだったら、そのまま普通に認知機能検査を受けましょう。
逆に言えば、お家などで少し試したときに覚えられないことが多ければ、それは認知機能検査でも同じようになるということです。
実際に検査を受けてみて、何も覚えてこない方が混乱しなくて良いってことがよく分かったよ。
記憶力が良いということはとても良いことですね(^^)
お家では試してみるだけにして、丸暗記はしないようにしましょう。
⬇︎⬇︎ こちらももう一度ご覧くださいね。
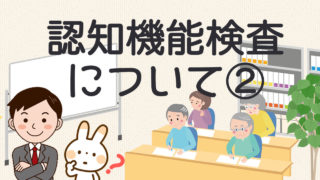
まだ「認知機能検査」が不安だったら
認知機能検査を受けて、とても勉強になったよ!
時間があるときにお家で試しに何回か受けてみるのは良いと思うよ♪
そうですね。お家で少しやってみるのはおすすめです。
ただもったいない間違い方をすると正しい検査結果は出ませんので、覚えるのではなくお試しでやってみるのが良いですね。
参考になる本は一度認知機能検査を試してみたい方向けです。
次の本は高齢者講習が変わっても為になる内容でオススメですよ。
本を買われない場合は、【認知機能検査が全てわかる!】体験談!認知機能検査を試しに受けてみた!(1)と、現在のページを「お気に入り」や「ブックマーク」にしておいてくださいね。
警察庁のサイトは ➡︎ こちら をクリックかタップ!
何度もお伝えするように、回答を覚えてしまったために間違える可能性も多いことも忘れないでくださいね。
「認知機能検査だけなんとかしたい」という考えはやめましょう。
「ちょっと知っておいて検査当日に不安でいないため」にしてね♪
安全に長く運転するために本当に必要なもの
「認知機能検査」を受けて、高齢者講習を受けて、いつか車やバイクの運転をしなくなる日まで、これからも安全運転を続けていくコツはあるのでしょうか?
もちろんあります!
まずは認知機能の低下を防ぐ生活をすること。そのためには「認知機能低下を知ること」がとっても大事です。
ちゃんと「認知機能の低下」や「認知症」と向き合ったことはありますか?
\ まずは「敵」知ることから!おすすめの本はこちら /
こちらの本は、「もの忘れ外来」を開設された先生の本です。認知症などの基本的なことが分かります。
だいたい1〜2時間で読めるのでおすすめですよ。
そして「認知機能の低下」を防ぐためにオススメなのが塗り絵です。
塗り絵は楽しみながらやってみるのが良いですね。
そして効果が高く、ちくたく指導員のお父さまもやっていたのが日記をつけることです。
塗り絵もやっていたそうですよ(^^)
私の父は「アルツハイマー型認知症」だったので、日記をつけることは効果があったようです。
日記をつけることは、先ほど紹介した「脳活性ノート」でもおすすめされているよ。
普通のノートに書いて大丈夫!(^^)
100円ショップにも売っていますし、昔からあるキャンパスノートなどでも大丈夫です。
日記はあとから思い出しながら書くことがおすすめです。
- 「今日は何を食べたかな?」
- 「勝った野球チームはどこだったかな?」
などを書いてみましょう。
普段から日記をつける習慣をつけると良いですね。
そして大切なのは身体機能の維持です。
お散歩をすることもとても良いですし、それが難しいと感じる場合は簡単な運動から始めましょう!
認知機能の低下を防ぎ体も健康でいることは安全運転につながりますし、何より高齢になってからの生活が楽しく過ごせるのです。
良いことばっかりだね♪
>> 【チェック!】新しい高齢者講習の対象になるか調べてみる
日頃から気をつけていれば、もし車やバイクの運転をやめても変わらず楽しく生活できますよね。
私も強くオススメします。
これからも安全運転を続けていく。
そのために「本当に必要なことは何だろう?」ということを考えることが何よりも大切なのです。
⬇︎⬇︎ こちらもご覧くださいね。
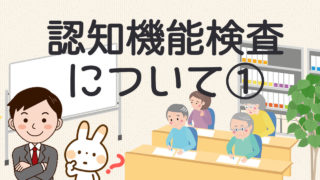
長い記事になりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。
ここまでしっかり読まれた方はきっと大丈夫。なぜなら「ちゃんと考えている」ということですからね(^^)
認知機能検査の当日に元気で検査を受けられるように、前日はよく寝て、忘れ物に気をつけて自動車学校・自動車教習所に行きましょう。
私たちの体験談が少しでも皆さまのお役に立てれば良いなぁと願っています。
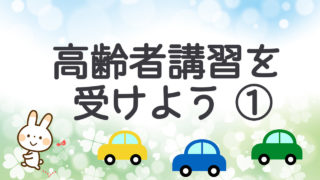
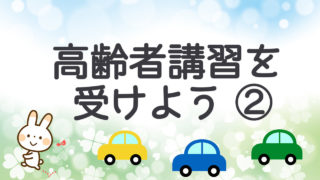
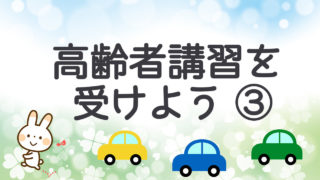
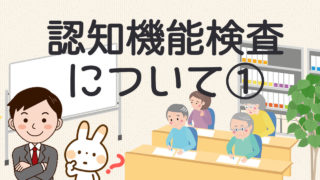
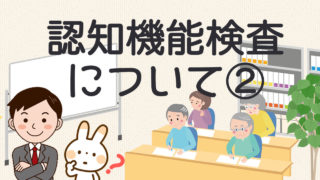
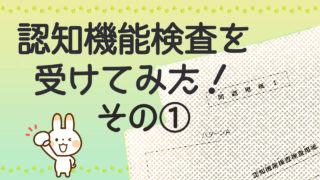



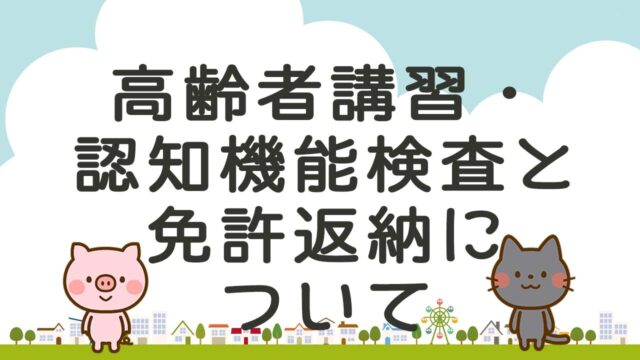

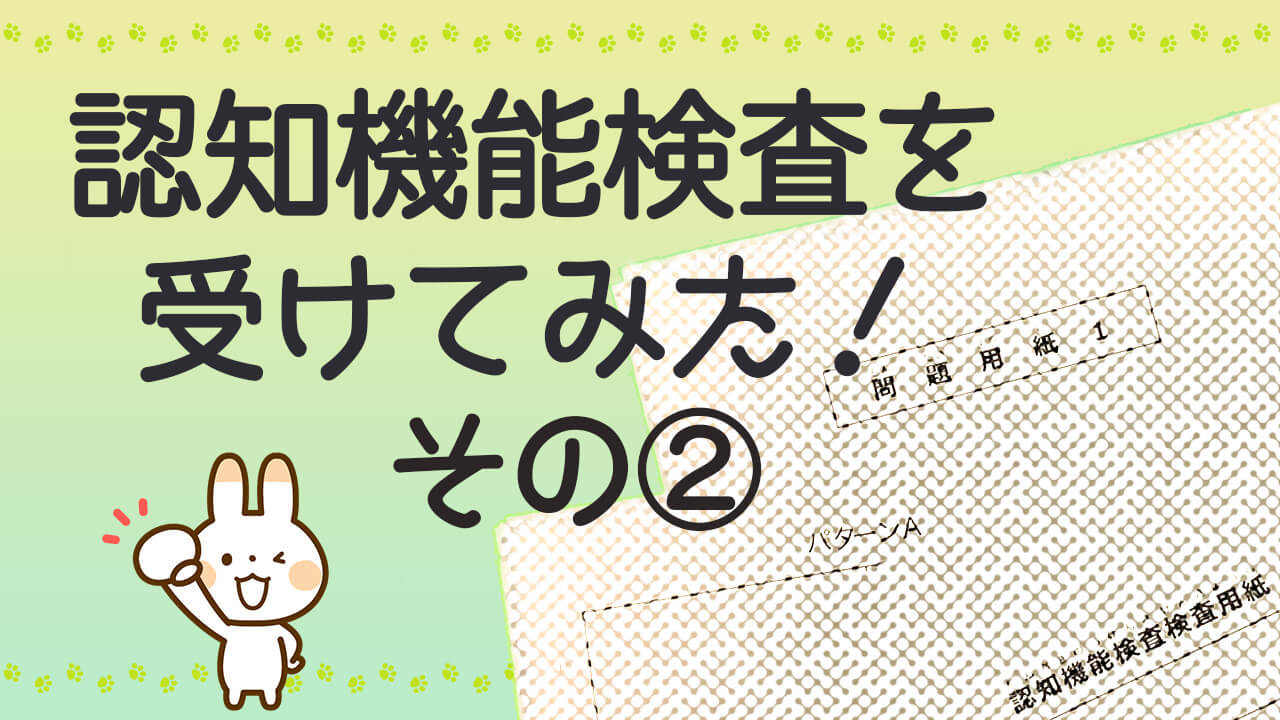








2.png)

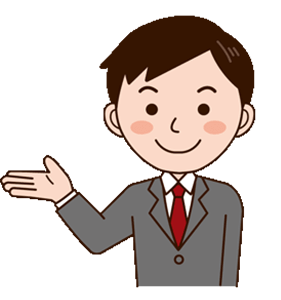






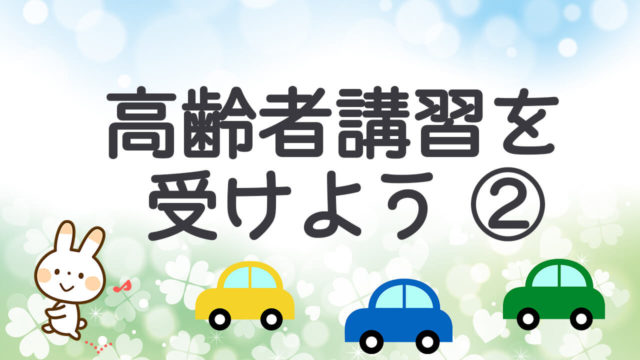
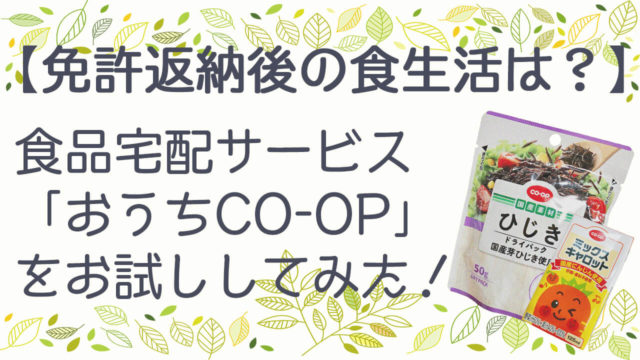
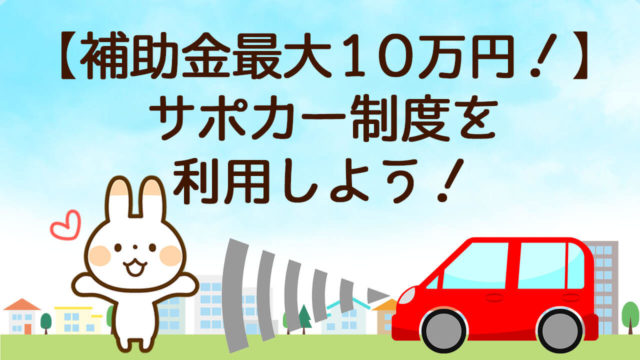

についてのコピー-320x180.png)

について-320x180.png)